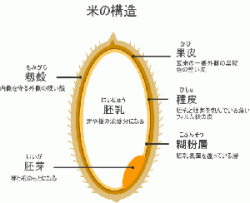玄米と白米

お米の収穫風景
近年、主食の座が怪しくなる程に食生活が変化してきていますが、それ以上に精白の度合いも進んでいて、今では白米が当たり前になってしまっています。
食べ物と健康を考えるとき、品目だけでなく、実際に食べている姿はより重要です。
前述した、ビタミンの発見につながったオリザニンは、米ぬかに含まれるビタミンであり、米の精白と密接に関係しています。
精白度が進んだことで、主食である米が、いつの間にか抱えてしまっている問題点について考えます。
江戸時代、参勤交代で江戸に行くと、体が重い・疲れやすいなどの体調不良を起こし、地元に帰ると自然に治るという愁訴があり、「江戸患い」と呼ばれました。
今考えると、精神的な要素もありますが、それ以上に精白された米などによるビタミン欠乏症(軽度の脚気)が疑われます。当時の食事は、主食であるコメを多量に摂取し副食が少なかったことから、江戸での生活で米の精白度が上がったため、ビタミンB1欠乏症に罹ったことが想像されます。
同様の現象が、現代の日本でも蔓延しており、肩がこる・体が重い・疲れやすい・眠い・物覚えが悪い・足がむくむ・手足がしびれるなど、軽度の脚気症状は主食の米が白米になっていることが原因かもしれません。
糖質や脂質の代謝によって私たちはエネルギーを得ていますが、この代謝過程に無くてはならないのがビタミンB1(チアミン)です。
今考えると、精神的な要素もありますが、それ以上に精白された米などによるビタミン欠乏症(軽度の脚気)が疑われます。当時の食事は、主食であるコメを多量に摂取し副食が少なかったことから、江戸での生活で米の精白度が上がったため、ビタミンB1欠乏症に罹ったことが想像されます。
同様の現象が、現代の日本でも蔓延しており、肩がこる・体が重い・疲れやすい・眠い・物覚えが悪い・足がむくむ・手足がしびれるなど、軽度の脚気症状は主食の米が白米になっていることが原因かもしれません。
糖質や脂質の代謝によって私たちはエネルギーを得ていますが、この代謝過程に無くてはならないのがビタミンB1(チアミン)です。
米などのイネ科の植物は,穎果(えいか)という果皮と種子が密着した構造をしている為、果皮を取る際に大切な栄養素を失いやすくなっています。マメ科の植物(落花生)と比較すると、最外層の硬い殻の部分がもみ殻、茶色の薄皮部分が玄米表面の茶色の部分ということになりますが、豆の様に簡単には除去できません。精米という、表面を削り取る作業が必要で、これに伴って胚芽に含まれる大切な栄養素が失われてしまいます。